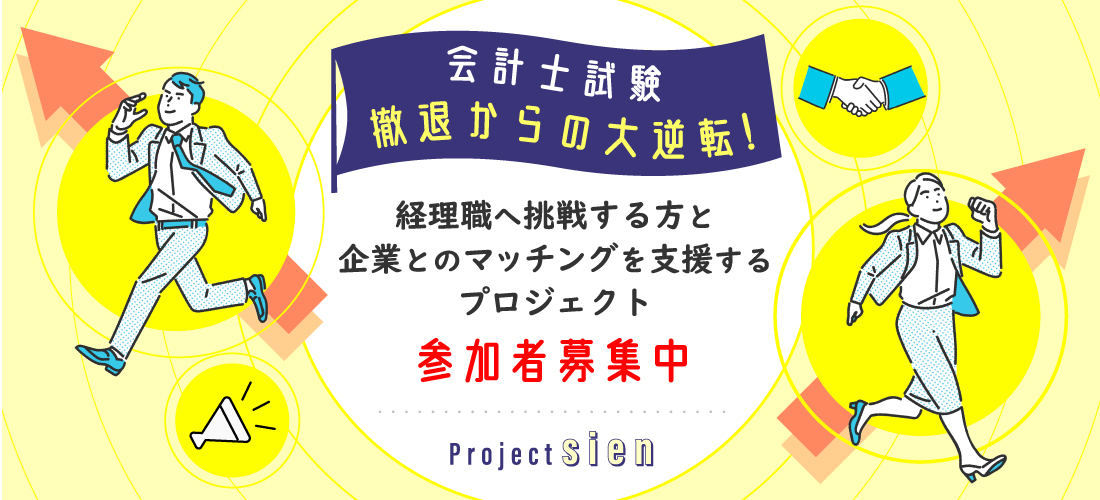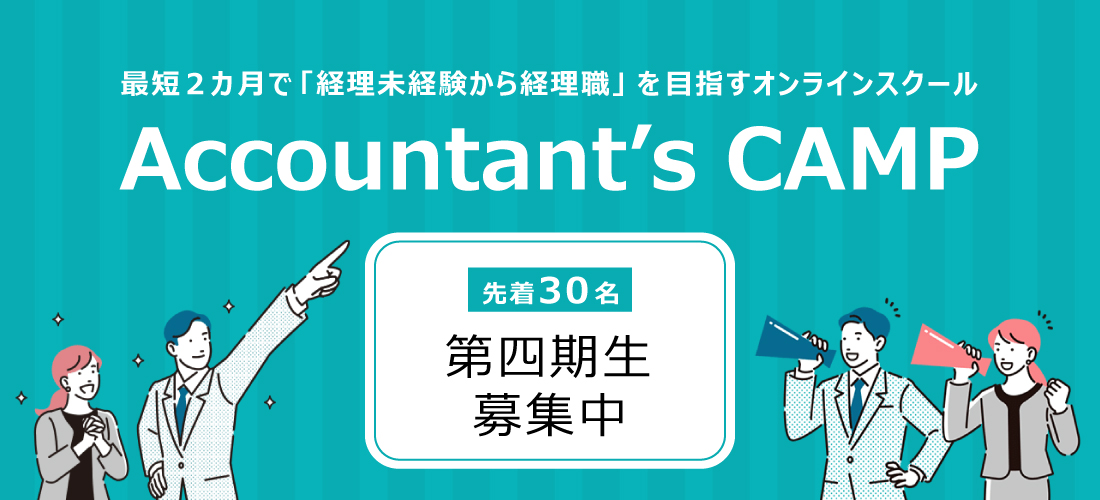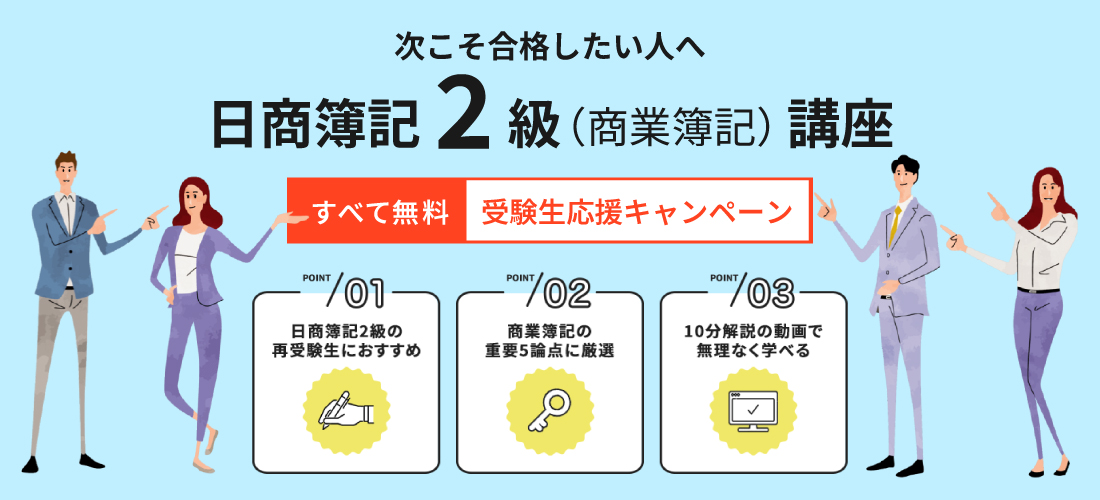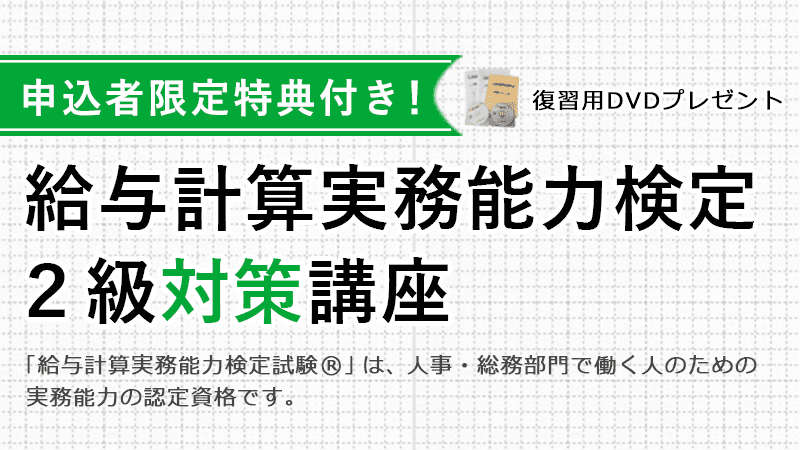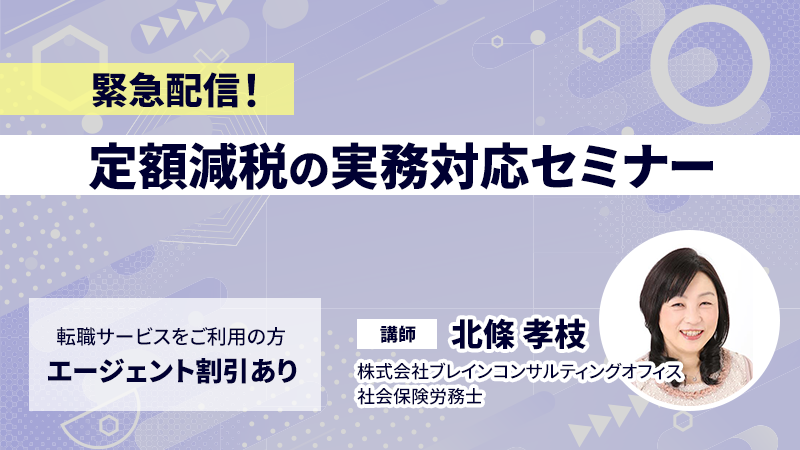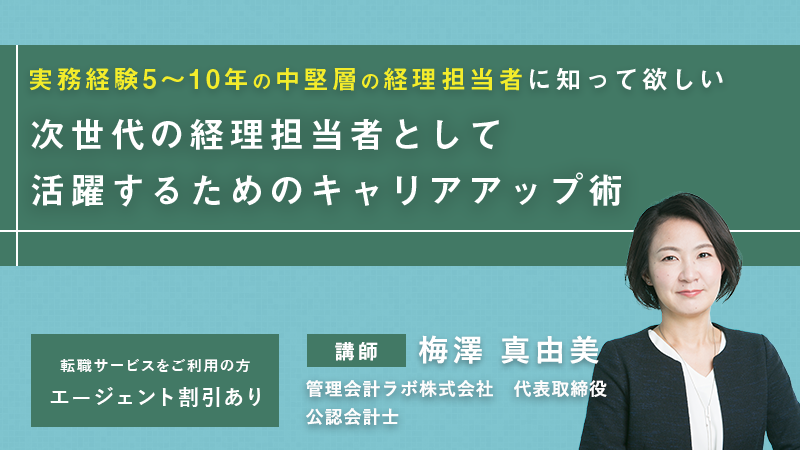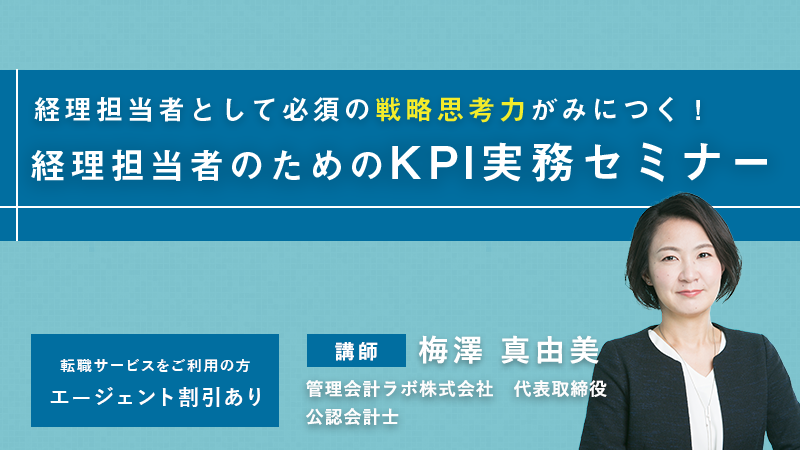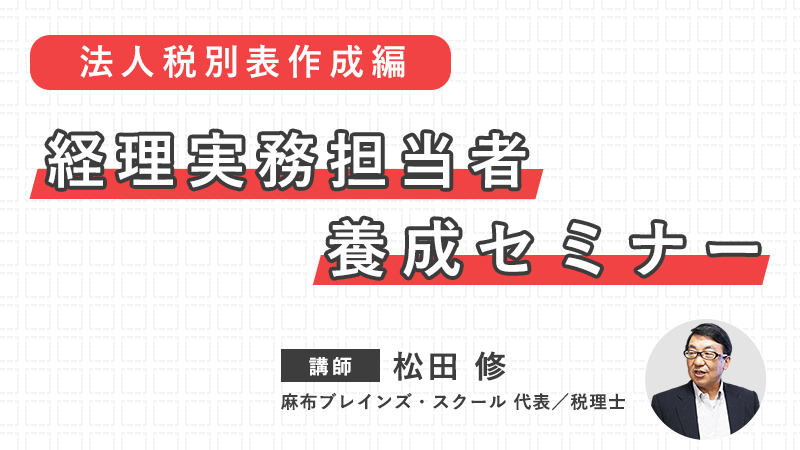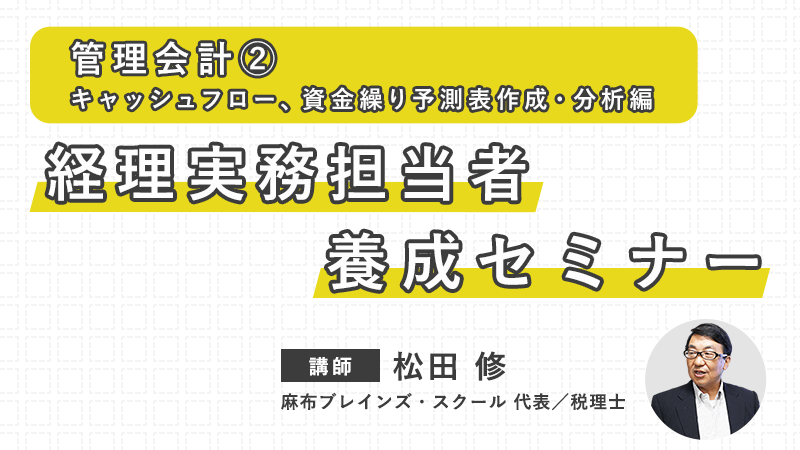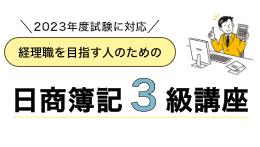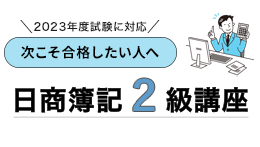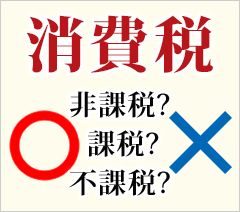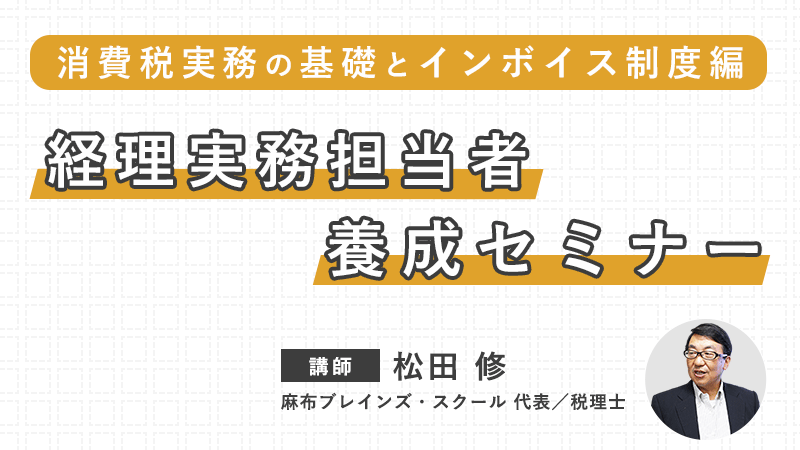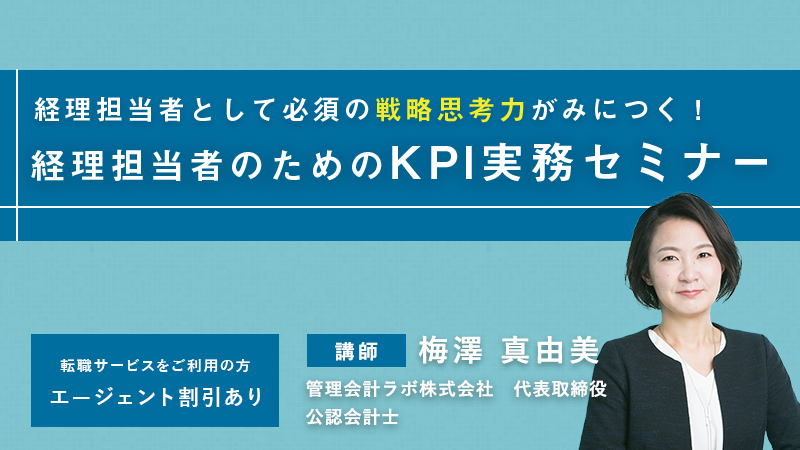ジャスネットコミュニケーションズ著者・企画書籍
今すぐ経理実務の知識を身につけたい方必読!
一番わかる!経理の教科書
「経理実務の学校」から生まれました
はじめてでもすらすらわかる!
すぐに使える仕訳例や勘定科目の使用例、帳票の記載例も充実!
全国の書店にて好評発売中!
2015年11月30日発行 定価 本体1,400円(+税)
A5判/240ページ/ISBN 978-4-7916-2330-3
第1章 経理を始めるための基礎知識
第2章 仕訳を制する者が簿記を制する
第3章 毎日行う現金と預金の管理を覚える
第4章 日々発生する経費精算は勘定科目がポイント
第5章 何かを買ったり売ったりするたびに記録する
第6章 何年も使うものは何年かに分けて計算する
第7章 月次決算でタイムリーな経営状況がわかる
第8章 給与計算をするのも経理の仕事
第9章 年次決算は経理の腕の見せどころ
第10章 デキる経理になるために!
経理の実務ですぐに使える内容が盛り沢山の一冊
本書を、今すぐ経理知識を身につけたいと切望する、経理未経験者の方々にお届けいたします。
経理知識を身に付けたくて簿記3級のテキストをぱらぱら読んでみた。
仕訳、勘定科目、決算書が作られるまでの流れはなんとなく掴めたけど、簿記と経理実務の差がよくわからない…。そんな悩みの解決ヒントになる本が本書です。
私たちジャスネットコミュニケーションズでは、創業来20年、延べ2万人を超える経理パーソンのキャリアに向き合ってきました。なかでも「経理実務の学校」では、簿記と経理実務の差を埋めるための教育教材を提供しています。
本書は、そのノウハウを活かし、実務でイメージしやすいように証票書類や申請書類のサンプルをふんだんに使いました。また、初学者が安心して経理処理ができることが重要であると考え、各業務内容に、毎日、適宜、毎月、毎年など、その処理の時期がわかるような工夫をしました。
まず1章と2章では、経理という仕事のイメージをつかみ、続く3章からは「現預金」「経費」「売上・仕入」など、業務ごとに章を分けて詳しく見ていきます。日常の業務から毎月(月次)の処理ときて、9章では経理の仕事の集大成である「年次決算」について解説します。そして最後の10章ではこれから経理を目指す方々へのささやかなアドバイスをお話しています。
このほかにも、コラムや用語集なども掲載しております。
このように本書は、経理の実務ですぐに使える内容が盛り沢山の一冊です。
私たちの経験からいえることは、「経理がわかれば人生が豊かになる」ということです。
そして、その魅力に気付くきっかけになるのがこの本です。
本書をお読みいただくことで、一人でも多くの経理で活躍を目指す方々にとってキャリアの参考となれば幸甚です。